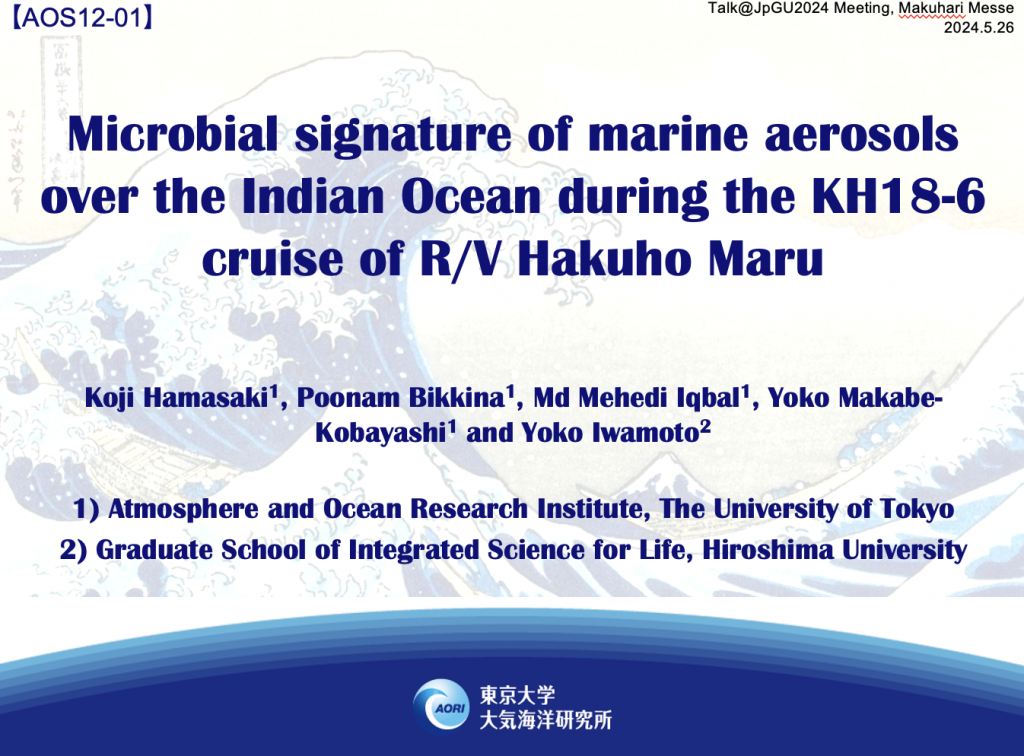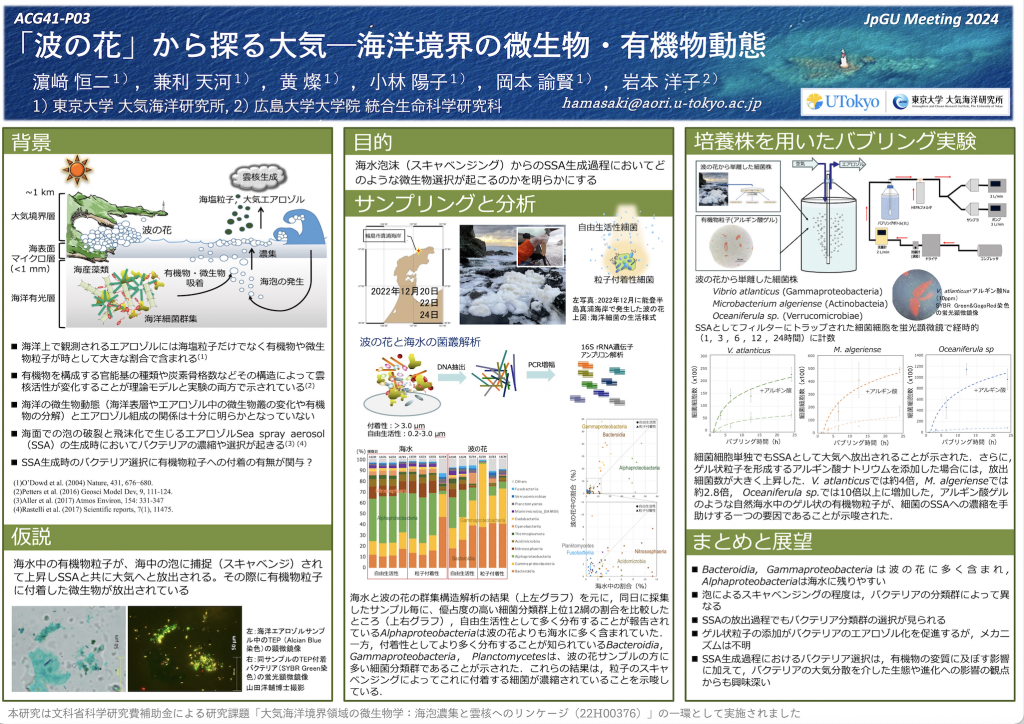6月初旬に、南フランス・ニースで開催された科学者会議One Ocean Science Congress(OOSC)に参加してきました。これは国連海洋会議(UNOC3, 6/9–13)の公式サイドイベントとして開催されたもので、科学と政策の架け橋としてCNRS(フランス国立科学研究センター)とIFREMER(フランス海洋開発研究機構)が共同主催し、世界各国の首脳・政府関係者、そして社会全体に向けて、海洋の健全性と未来を示す科学的知見を届けることを目的としたイベントです。
会場はニース港全体を封鎖して設営され、街はこの会議に向けて1年以上にわたって準備を重ねてきたそうです。この会議に合わせて、ニース港には世界中から個性的な船が集結していました。ここではその中から、いくつか印象的だった船たちをご紹介します。
Statsraad Lehmkuhl(ノルウェーの帆船)
美しい帆と装飾を備えたノルウェーの大型帆船。「One Ocean Expedition 2025–2026」の一環として世界を航海中で、海洋教育・環境啓発に活用されているそうです。

Energy Observer(フランス)
世界初の水素と再生可能エネルギーによる自律航行船。太陽光、風力、水素燃料電池を組み合わせ、エネルギー自給を達成しています。こちらも地球一周の航海を通じて、未来の持続可能な技術の可能性を広めているそうです。

Team Maliziaの「SCIENCE」ヨット(ドイツ)
プロセーラーBoris Herrmannが率いるレーシングヨット。「A Race We Must Win」キャンペーンの一環として、科学と教育を融合した取り組みを展開。Max Planck研究所やGEOMARと連携し、航海中に海洋データを収集する船上ラボを備えており、世界の子どもたちへの教育活動「My Ocean Challenge」も展開中とのこと。 
Artexplorer(フランス)
世界初の「海に浮かぶデジタル美術館」。巨大な双胴ヨット。文化財団が主導するプロジェクトで、海と芸術、地域と人をつなぐ旅を展開中。


Baía Farta(アンゴラの研究船)
アンゴラの国家海洋プログラム「Kalunga Programme」に基づき建造された海洋調査船。説明を読むと、ROVも搭載した最新鋭船のようですが、アンゴラの海洋学の現状はどんな感じなんでしょうか。

GAIA BLU(イタリア、研究船)
イタリアの国家研究機関が運用する調査船。最新の観測装置を備え、地中海を中心に海洋科学研究を支援しています。元はドイツの研究船だったみたいですが、最近イタリアに移管されたようです。